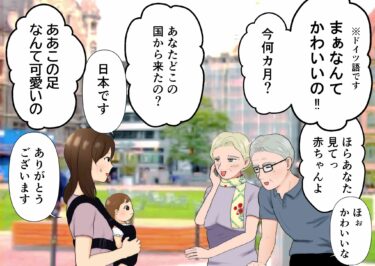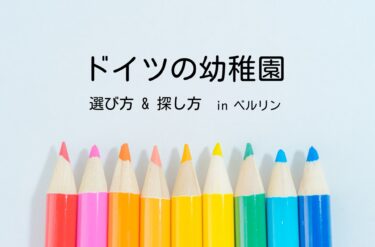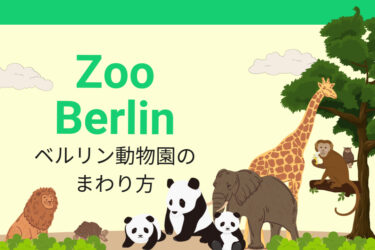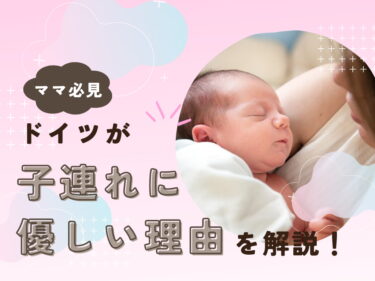これからドイツでの生活を予定している方の多くが、子育て環境について疑問や不安を感じているのではないでしょうか。
この記事では、
をテーマに、
体験談を交えながら子育ての悩み解決方法をお伝えします!
子連れでドイツへ駐在を予定している方へ、これからのドイツ生活を安心してスタートさせるために、役立つ情報が満載です。
記事の前半では「ドイツでの子育てのメリット・デメリット」について解説し、
記事の後半では「海外育児の成功のコツ」について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
それでは本編です!
- ドイツでの乳幼児子育ての実態
- 0歳・2歳児を連れた海外生活の体験談
- 日本との子育て文化の決定的な違い
- ドイツ子育ての実践的なノウハウ
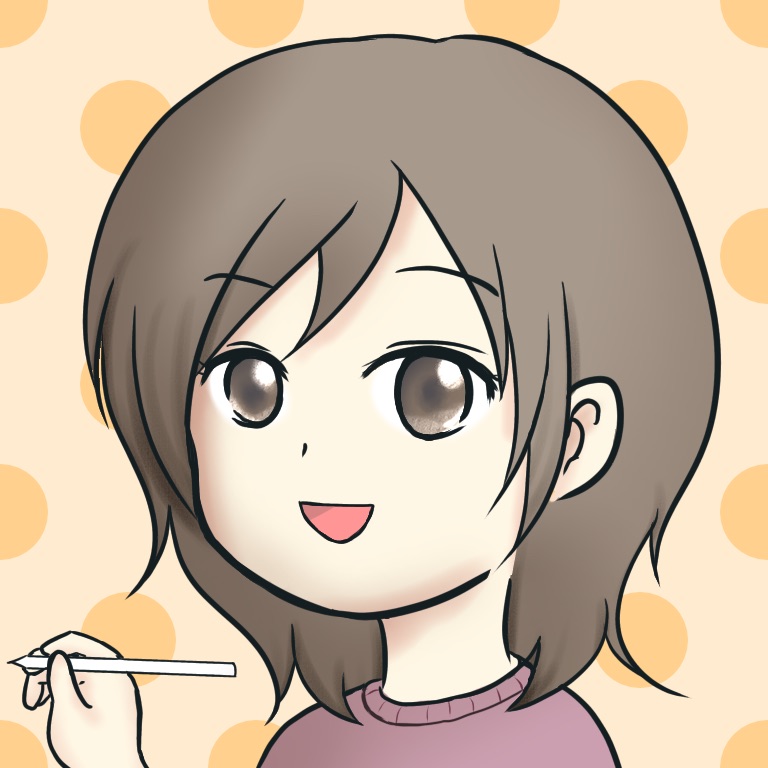
ドイツ・ベルリンで3年間の駐在経験
0歳、2歳時を連れて夫の海外赴任に帯同
語学学校で2年間ドイツ語を学習→C1まで習得
帰国後、経験を活かして駐在妻向けブログを運営中
ドイツ子育ての魅力とは?
ドイツが子育てしやすい国である5つの理由を解説します。
- 子どもに優しいドイツの人々
- 充実したベビーグッズ
- 公園と自然環境が豊富
- 外国人向けのドイツ語コース
- 幼稚園が無料
それぞれ解説していきます。
子どもに優しいドイツの人々
ドイツの街を子連れで歩いていて最初に驚いたのは、子どもに対する周囲の寛容さ。
日本では公共の場で気遣うことが多い子育てですが、ドイツではむしろ積極的に支援してくれる雰囲気がありました。
具体的例
- 地下鉄の階段でベビーカーを運ぶ際、自然に手伝ってくれる
- バスや電車では、ベビーカーのためにすすんで席を譲ってくれる
- 子どもが少し騒いでも、温かい目で見守ってくれる
| 子育て環境の比較 | 日本 | ドイツ |
|---|---|---|
| 公共交通機関 | ベビーカーへの視線が気になる | 積極的に場所を作ってくれる |
| 子どもの声 | 周囲に気を遣う | 寛容に受け入れられる |
| 周囲の反応 | 遠慮がち | 協力的で積極的 |
日本だと肩見狭い思いをしながら公共の場に子どもを連れていきますが、ドイツでは老若男女問わず温かく見守ってくれる雰囲気でした。
具体的なエピソードはこちらにまとめています。
Mia こんにちは、元ドイツ駐在ママのみあです! 一昔前、このようなニュースが話題になったことをご存知でしょうか。 さっき5人しか乗っていないガラガラのバスでベビーカーを専用座席にベルトで固定し[…]
言葉の壁はありますが、その壁を軽く超えられるほどの優しさがドイツにはありました。
💡ドイツ生活のアドバイス
- 困ったときは遠慮せず周りに助けを求めましょう
- 笑顔で「Danke(ありがとう)」の一言で、さらに良好な関係が築けます
充実したベビーグッズ
ドイツは高品質なベビーグッズが充実しています。
ベビー用品を3つの項目に分けて、具体的に解説していきます。
1. ベビーキャリー
ドイツのベビー用品は種類が豊富で、多機能型からコンパクトなものまで、さまざまなニーズに応える商品が揃っています。
特に、
- ベビーカー(サイベックス、バガブー、トイトニア)
- チャイルドシート(マキシコシ、ローマー)
- 抱っこ紐(エルゴベビー、ベビービョルン)など
は欧州安全規格(EN基準)をクリアしたものが一般的で、安心して選ぶことができます。
2. ベビー消耗品
私が初めてドイツのドラッグストアに訪れたとき、ベビー用品の充実ぶりに驚きました。
特に、オーガニック素材で作られたベビースムージーは、ドイツ生活の愛用品でした。
ベビーフード
- 豊富な種類と選択肢
- オーガニック商品が充実
- おすすめ商品:オーガニックベビースムージー「フルッフバー」(写真あり↓)

おむつ類
- サイズの種類が豊富
- メーカーの種類が豊富
- テープタイプ、パンツタイプ、水遊びタイプあり

おむつも選択肢が幅広く、メーカーやデザイン、素材(オーガニックコットンなど)によって選べます。
3. スキンケア商品
日本でも人気のヴェレダ(WELEDA)のスキンケア商品が、ドイツのドラッグストアでは手軽に購入可能です。
- ヴェレダ(WELEDA)などの高品質ブランド
- オーガニック志向の商品が豊富
- 低刺激処方が一般的

公園と自然環境が豊富
ドイツは公園や自然環境が豊かで、子どもたちがのびのびと遊べる場所が多くあります。
中でも驚かされたのが、まるでアスレチックのような魅力的な遊具の数々!

都市部でも緑が多く、週末には家族で森や湖に出かけるなど、自然を楽しむ機会が豊富にあります。
Mia こんにちは、元ドイツ駐在ママのみあです。 今回はドイツで3年間子育てをした経験をもとに、ドイツの公園についてのお話をしたいと思います! 海外の公園事情を知りたい人 子連[…]
外国人向けのドイツ語コース
ドイツでは外国人がドイツ語を学ぶためのコースがたくさんあります。
私もドイツの市民学校を利用して、語学学校に通いました。

移住者や駐在者、子連れの親に特化したプログラムも充実しております。
以下に、それぞれのコースや学校について解説します。
1. インテグレーションコース(Integrationskurs)
ドイツ政府が提供する「統合コース」は、移住者がドイツ語を学びながら、生活や文化についても学ぶことができるプログラムです。
コース内容は以下の通りです。
- 言語学習: 初級から中級(A1~B1レベル)まで対応。
- 生活ガイド: ドイツの法律や文化、公共サービスの利用法について学習。
- 費用: 一般的に低価格(場合によっては無料)。
- 特徴:託児所付きコースあり。
地域のVHS(ホルクスホッホシューレ)や認定された語学学校で受講できます。
2. プライベート語学学校
ベルリンやミュンヘンなどの都市部では、多くのプライベート語学学校があります。
基本的に高価格ですが、資格取得や個別指導など専門的なコースが充実しているのが特徴です。
有名な学校例
- Goethe-Institut(ゲーテ・インスティテュート): 国際的に認知された資格が取得可能。
- Berlitz(ベルリッツ): 個別指導やオンラインクラスが充実。
3. オンラインコース
通学が難しい方にはオンラインで学べるコースが便利です。
- Duolingo: 自分のペースで進められる初級向けアプリ。
- Deutsche Welle(DW): 無料のオンライン学習リソースを提供。
オンライン学習リソースに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
ドイツへの駐在が決まったものの、 「ドイツ語の勉強、どこから始めればいいんだろう?」 「ドイツで英語は通じるから、ドイツ語は本当に必要なの?」 といった不安を抱えていませんか? この記事では、ドイツ語[…]
以上の3つが、外国人向けのドイツ語を学ぶ方法です。
ドイツ語コースを選ぶ際は、費用、目的、通学のしやすさを考慮することが重要です。
初めは地域のVHSやインテグレーションコースで基礎を固め、その後に専門性や資格取得を目指すことがおすすめです。
幼稚園が無料
ドイツでは、多くの州で幼稚園(通称:Kita)が無料(または非常に低料金)で利用できます。
ドイツ国民だけでなく、我々のような外国人家庭にとってもありがたい仕組みです。

以下に詳しく解説します。
1. 幼稚園が無料になる理由
ドイツ政府は少子化対策や子育て支援政策の一環として、幼児教育への投資を強化しています。(参考元:OECD-iLibrary)
一部の州では、すべての子どもが無料で幼稚園に通えるような政策を採用されています。
2. 無償化の条件
無償化には以下のような条件があります。
- 住民登録をしていること
- 所得証明や特定の書類の提出が必要な場合がある
外国人だから対象外ということはなく、我々のような駐在家族も対象になったので、とても助かりました。
3.注意点
無償化されている場合でも、給食費や延長保育費は別途請求されることがあります。
また、都市部では幼稚園の待機リストが長く、早い段階での申し込みが必須です。
ドイツの幼稚園についての記事はこちらに詳しく書いています。
興味があれば参考にしてください。
本記事では、実体験をもとに、 ドイツでの幼稚園探し を徹底解説します。 ドイツへの赴任が決まった家族にとって、最も重要な課題の一つが幼稚園探しです。 日本とは異なる制度や環境の中で、 […]
ドイツ生活で苦労するポイント
ドイツでの育児生活は魅力的ではありますが、その一方で色々と大変に感じる面も多くあります。
以下では、私達家族だけでなく、多くの駐在者や移住者が感じる苦労と、その対策をご紹介します。
- 言葉の壁
- 日常の不便さ
- 保育施設不足
- 家族のサポートが少ない
- 緊急時の医療対応
- 文化の違いによる戸惑い
- 子どもの友達作り
事前に心構えをしておくことで、海外生活をよりスムーズにスタートできると思います。
それぞれ詳しく解説していきます。
言葉の壁
まず直面するのは言葉の壁です。
ドイツ語だけでなく英語も話せないとなおさら、コミュニケーションで苦労します。
苦労する理由
- ドイツ語は初心者にとって習得が難しい
- 地方では英語が通じないケースが多い
- 買い物、役所手続き、学校や幼稚園との連絡に支障あり
対策
- 基本的なドイツ語フレーズを事前に学習する
- 翻訳アプリを活用する
- ドイツ語コースを受講する
Mia こんにちは、みあです! 3年間のベルリン駐在生活で、 英語もドイツ語もほとんど話せない状態から 両言語でコミュニケーションが取れるようになった 経験があります。 […]
日常の不便さ

日本と比べて店の営業時間が短く、日曜日はほとんどの商店が閉まっています。
また、公共交通機関の遅延や運行スケジュールの変更により、移動が計画通りに進まないことも珍しくありません。
直面する課題
- 店舗の営業時間が短い
- 日曜日は大半の店舗が休業
- 公共交通機関の遅延や予定変更が頻繁
対策
- 週末までに買い物をまとめて済ませる
- 徒歩や自転車など、複数の移動手段を確保する
- 余裕をもった行動計画を立てる
保育施設不足
ドイツでは都市部を中心に、保育施設の供給が需要に追いついていません。
特に幼稚園(Kita)の待機リストは長く、仕事を始めるタイミングに子どもを預けられない場合があります。
実際、我が家も幼稚園に入れるまでに1年かかりました。
課題
- 特に都市部では保育施設が不足している
- 幼稚園(Kita)の待機リストが長期化するケースあり
- 仕事開始に間に合わないケースも
対策
- できるだけ早期に情報収集を開始する
- 現地のコミュニティを活用する
家族のサポートがない
日本で親戚や家族のサポートを受けていた場合、ドイツでは物理的にそれが難しくなります。
実家から日本の食材や日用品を送ってもらうことはできても、日常的な育児のサポートは受けられず、不安を感じることもあると思います。
直面する課題
- 日本のような家族からのサポートが得られない
- 緊急時の対応に不安あり
- 子育ての相談相手が限られる
対策
- 信頼できるベビーシッターの確保
- 駐在仲間や近所のグループと協力
- オンラインコミュニティの活用
緊急時の医療対応

ドイツの医療制度は比較的しっかりしていますが、かかりつけ医制度・予約制が一般的な上、緊急時にすぐ診てもらえるとは限りません。
また、医療スタッフとの言語の壁も大きな課題です。
医療面での課題
- 予約制が基本で緊急対応が遅い場合がある
- 医療スタッフとの言語の壁
- 日本との医療システムの違い
対策
- かかりつけ医を早めに確保する
- 緊急時の連絡先リストを作成する
- 医療通訳サービスの事前登録
文化の違いによる戸惑い
ドイツでは育児の考え方や教育方針が日本とはいくつかの面で異なりますが、それゆえ、親同士のコミュニケーションで戸惑うことがあります。
具体的な違いとして以下が挙げられます。
1. 早期自立を促す教育方針
ドイツでは自立心をはぐくむために、乳幼児を早い段階で母子別々に寝かせる習慣があります。
逆に日本では、親子同室で寝る習慣を続けている家庭が多く締めています。
2. 父親の育児参加への意識の高さ
ドイツでは「両親手当」や男性の育児休業取得を促進する制度が整っており、男性の育児参加率が日本に比べて高いです。
私も実際に、平日の昼でも父親が公園に連れてくる姿が多く見られて驚いた記憶があります。
3. 学校や幼稚園での教育方法
ドイツの幼児教育では、のびのびとした自由な活動が重視されており、子どもの自主性を尊重します。
逆に日本では、協調性や規律を重んじた教育が多く、幼稚園の先生や親同士の価値観の違いに戸惑うことが多々あります。
以上が日本とドイツの教育の違いです。
これらの違いをあらかじめ理解しておくことで、異文化間のギャップを減らすことができます。
子どもの友達作り

言葉や文化の違いから、子どもが新しい環境で友達を作るのに苦労することがあります。
特にコミュニケーションが苦手な子どもは、言葉の壁も相まって学校や幼稚園でのいじめや孤立も懸念されます。
課題
- 言語の壁による友達作りの難しさ
- 文化の違いによる戸惑い
- いじめや孤立のリスク
対策
- 現地の子ども向けアクティビティへ積極的に参加する
- 段階的に環境適応のサポートをする
- 学校・幼稚園と密にコミュニケーションをとる
子育てを成功させるコツ
以上がドイツでの子育てのメリット・デメリット」について解説しました。
ここからは、ドイツで子育てを成功させるコツについてお話しします。
情報収集の方法
ドイツで子育てを成功させるためには、情報収集が鍵です。
以下の方法を活用して、必要な情報をスムーズにゲットしましょう!
- オンラインコミュニティの活用
- 現地コミュニティの活用
- 地域の情報源の活用
1.オンラインコミュニティの活用
当サイトを含め、ブログ、YouTube、SNSなど、海外での子育て情報を発信しているサイトを活用しましょう。
「ドイツ 子育て」「海外駐在 子連れ」などのキーワードで検索するのがおすすめです。
2.現地コミュニティの活用
ソーシャルメディアや地域の日本人会を通じて、同じ環境で子育てをしている家庭とつながることで、実体験に基づくアドバイスが得られます。
実際に私も、現地コミュニティが一番生活に身近な情報を得ることができました。
現地コミュニティはつながるまでが大変ですが、積極的にコミュニティに参加して家族構成が近い家庭と連絡先を交換することをおすすめします。
3.地域の情報源の活用
市役所や地域の支援センターで子育て関連の情報を収集することもできます。
日本語での対応は期待できませんが、シンプルな英語でも通じることが多いです。
地域の情報源
- 地元の市役所(Rathaus)で子育て関連の情報を収集
- 地域の家族センター(Familienzentrum)を訪問
- 幼稚園や学校の情報セッションに参加
子連れで楽しむドイツ生活

家族向けサービスの活用
ドイツは日本よりも家族で楽しめるサービスが豊富にあります。
ファミリー割引サービスを活用することで、動物園や博物館への入場料を節約することも可能です。
家族向けイベントとアクティビティ
- 無料の家族イベントに参加
- 博物館の子供向けプログラム
- 公園や遊び場でのファミリーイベント
Mia こんにちは、元ドイツ駐在ママのみあです! 今回は子連れの方におすすめするベルリンの観光スポットをご紹介します。 ベルリンに在住中の方も、旅行で来る方にも! 3年間のベルリン駐[…]
子育て文化の違いを楽しむ
ドイツの子育て文化には日本とは異なる魅力があります。
例えば、子どもの自主性を尊重する教育方針や、のびのびと遊べる広大な公園などがあちこちにあります。
日本との文化違いを理解し、子どもと一緒に新しい文化を楽しむ姿勢が大切です。
一例として、こちらの記事で紹介している動物園は、遊びながら自然を学べる環境が充実しているので、是非目を通してみてください。
Mia こんにちは、元ドイツ駐在ママのみあです! ベルリン動物園は駐在中、年間パスポートを購入してたくさん入園しました。 このブログでは、ベルリンに3年間子連れで駐在した経験をも[…]
よくある疑問と解決策
最後に、ドイツでの子育てに関するよくある質問にお答えします。
まとめ:ドイツ子育てを楽しもう
ドイツでの子育てには、魅力的な面と不安が共存していますが、事前に準備をして柔軟な対応をすれば、家族全員が楽しく充実した海外生活を送ることができます。
新しい文化や環境を子どもと一緒に楽しみながら、ドイツならではの子育て体験を満喫しましょう!
最後に、ドイツ子育て生活を楽しむポイントをまとめました。
・文化の違いを受け入れる
・新たな経験を積極的に楽しむ
・他の家族や現地の人々との交流
・サポートネットワークの構築
・困難を学びの機会と捉える
・子供の成長を楽しむ